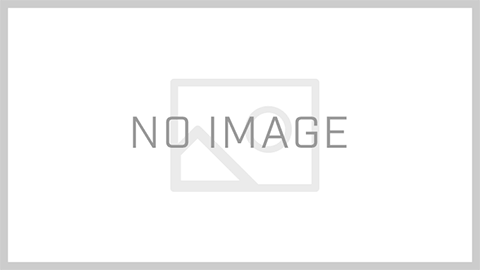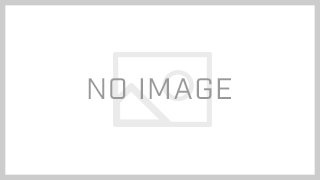- プロ野球の交流戦について詳しく知りたい
- 交流戦のルールや順位の決め方は?
- 交流戦の通算成績や各年度の優勝球団を教えて
毎年大きく盛り上がる、プロ野球の交流戦。しかし、開催時期や順位の決め方、ペナントレースとの関係性など、気になる部分も多いです。
筆者はプロ野球を30年以上観てきました。交流戦も開催初年度から楽しんでいます。
そこでこの記事では、交流戦のルールや通算成績、魅力までまとめて解説します。
この記事を読めば、交流戦に詳しくなり、今以上に交流戦を楽しめます。
\加入月無料!12球団全試合が見られる/
→【利用体験談あり】スカパー!プロ野球セットの料金は高い?評判や契約手順・支払い方法まで徹底解説

プロ野球の交流戦とは「別リーグのチームとの試合」

プロ野球の交流戦とは「普段は同リーグ内で対戦しているチームが、別リーグのチームと対戦する試合」。セリーグのチームはパリーグのチームと、パリーグのチームはセリーグのチームと対戦します。
交流戦の正式名称は「日本生命セ・パ交流戦」で、2005年から始まりました。
開催時期はその年によって異なりますが、近年は5月下旬から6月中旬に行われています。
交流戦以外での別リーグとの試合といえば、オープン戦や日本シリーズ。
オープン戦や日本シリーズと異なる交流戦の特徴は、交流戦の成績がシーズン成績に含まれる点です。
交流戦の成績がシーズン成績に含まれるので、チームや選手にとって、交流戦の期間も大変重要です。
なお、2020年は新型コロナウイルスの影響により、2005年に交流戦が開始されて以降、初めて交流戦が中止となりました。
交流戦の試合数
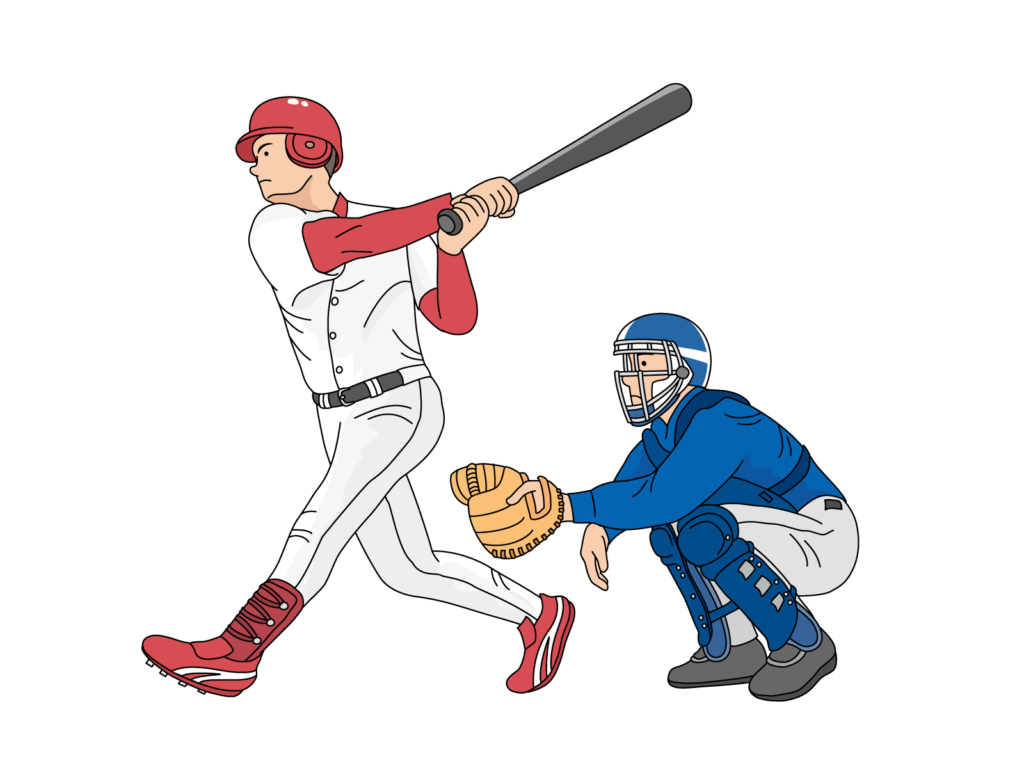
2025年現在、交流戦の試合数は1チーム18試合です(1カード3試合×1カード×6球団)。
例として、2025年の阪神タイガースの交流戦日程を見てみましょう。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 6/2 | 3 日本ハム | 4 日本ハム | 5 日本ハム | 6 オリックス | 7 オリックス | 8 オリックス |
| 6/9 | 10 西武 | 11 西武 | 12 西武 | 13 楽天 | 14 楽天 | 15 楽天 |
| 6/16 | 17 ロッテ | 18 ロッテ | 19 ロッテ | 20 ソフトバンク | 21 ソフトバンク | 22 ソフトバンク |
6球団のうち、3球団との試合をホーム(自チームの球場)で行います。現在の18試合の場合、対戦相手の6球団全てをホームで見るには2年が必要です。
交流戦の過去の試合数
2005年の交流戦開始当初から、試合数は以下のように変化しています。
| 年 | 試合数 |
| 2005~2006年 | 36試合(1カード3試合×2カード×6球団) |
| 2007~2014年 | 24試合(1カード2試合×2カード×6球団) |
| 2015年~ | 18試合(1カード3試合×1カード×6球団) |
交流戦開始時は36試合でしたが、現在は18試合に減少しています。
交流戦の試合数が減少している理由
交流戦の試合数が減少している理由として、セリーグからの強い要望が挙げられます。
交流戦で巨人や阪神といった人気球団と対戦できるパリーグ球団は、観客数の増加が見込めます。一方で、巨人や阪神との試合が減るセリーグ球団は、観客数が減少する傾向に。
観客数を考えた場合、セリーグ球団が交流戦の試合数減少を要望する気持ちは理解できます。
交流戦のルール
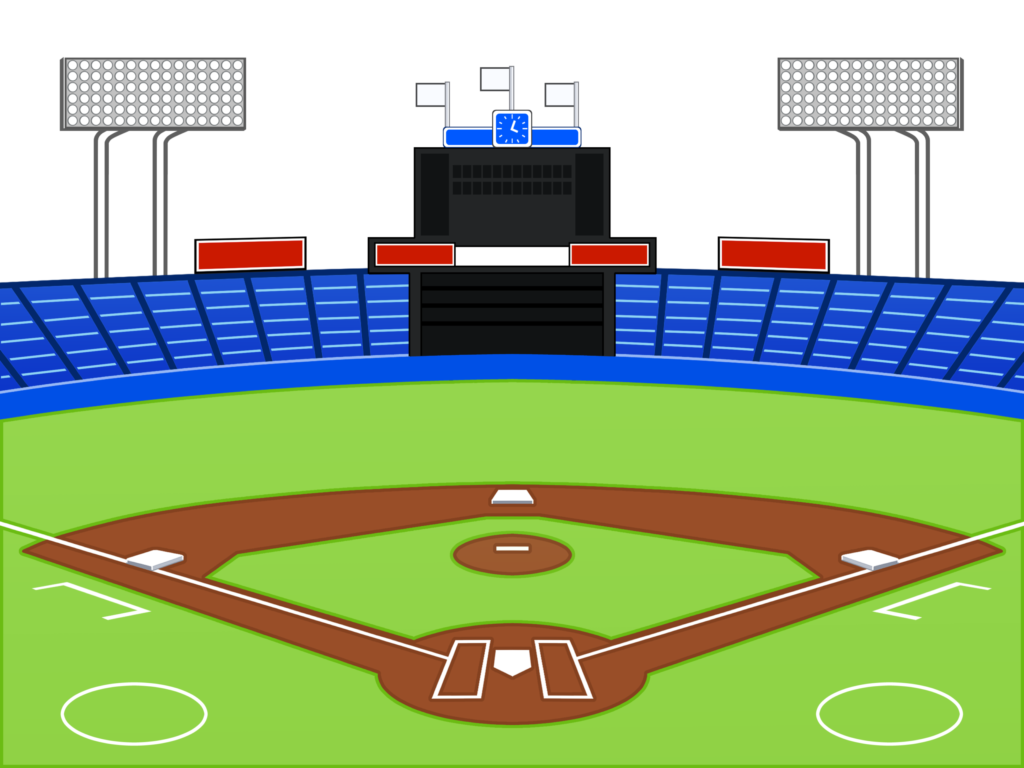
- 指名打者
- 予告先発制度(2012年~)
- 延長戦
- 順位の決め方
指名打者
指名打者とは、投手の代わりに打席に立つ、攻撃専門の選手。パリーグ球団の主催試合で採用されています。
交流戦でも、パリーグ球団の主催試合でのみ、指名打者が採用されています。
なお、過去の交流戦では、2014年にセリーグ球団の主催試合でのみ指名打者を採用したことがありました。
予告先発制度(2012年~)
予告先発は、先発投手を事前に発表する制度。交流戦では2012年から導入されています。
実は交流戦開始当初、パリーグでのみ予告先発を実施しており、セリーグでは実施していませんでした。しかし、2012年にセリーグも予告先発を導入したことにより、交流戦でも予告先発が実施されるように。
予告先発によって、エースが登板する試合や、自分の好きな投手を球場で確実に観られるので、集客アップにつながります。
延長戦
2025年現在、延長戦は12回までです。
交流戦の順位の決め方
交流戦では、勝率第1位球団を「交流戦優勝球団」として表彰します。
勝率が並んだ場合、以下の条件で順位を決定します。
- 勝利数
- 交流戦の直接対決成績(3チーム以上並んだ場合は省略)
- 交流戦18試合のTQB(得失点率)-《(得点/攻撃イニング)-(失点/守備イニング)》が大きいチーム
- 交流戦18試合のER-TQB《(相手自責点による得点/攻撃イニング)-(自責点/守備イニング)》が大きいチーム
- 交流戦18試合のチーム打率
- 前年度交流戦の順位
交流戦の通算成績
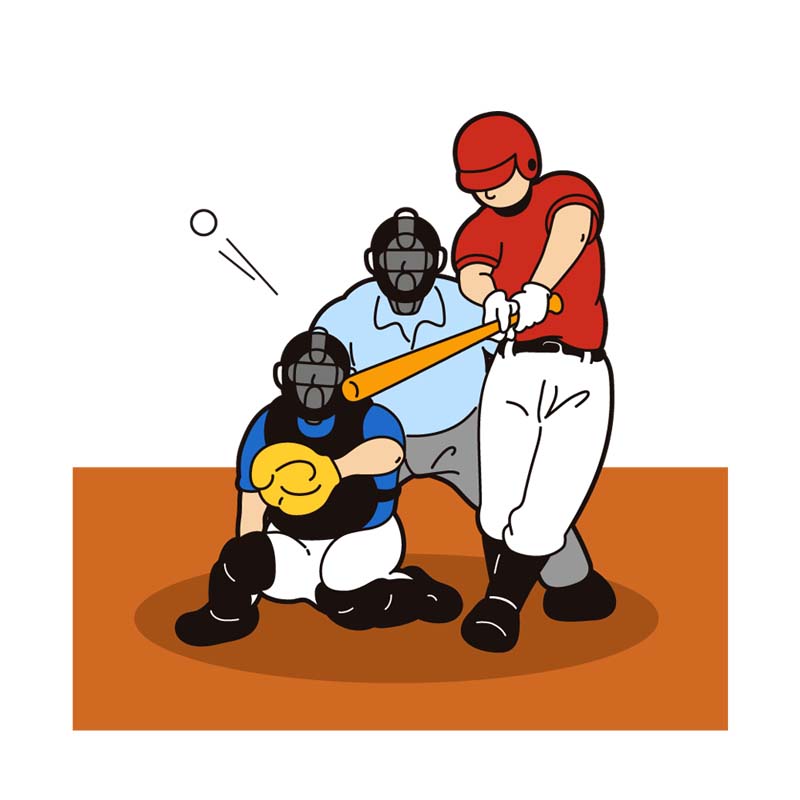
交流戦の通算成績をご紹介します。
リーグ間の対戦成績
| 年度 | セリーグ | パリーグ | 引き分け |
| 2005年 | 104勝 | 105勝 | 7 |
| 2006年 | 107勝 | 108勝 | 1 |
| 2007年 | 66勝 | 74勝 | 4 |
| 2008年 | 71勝 | 73勝 | 0 |
| 2009年 | 70勝 | 67勝 | 7 |
| 2010年 | 59勝 | 81勝 | 4 |
| 2011年 | 57勝 | 78勝 | 9 |
| 2012年 | 66勝 | 67勝 | 11 |
| 2013年 | 60勝 | 80勝 | 4 |
| 2014年 | 70勝 | 71勝 | 3 |
| 2015年 | 44勝 | 61勝 | 3 |
| 2016年 | 47勝 | 60勝 | 1 |
| 2017年 | 51勝 | 56勝 | 1 |
| 2018年 | 48勝 | 59勝 | 1 |
| 2019年 | 46勝 | 58勝 | 4 |
| 2020年 | 中止 | 中止 | 中止 |
| 2021年 | 49勝 | 48勝 | 11 |
| 2022年 | 55勝 | 53勝 | 0 |
| 2023年 | 52勝 | 54勝 | 2 |
| 2024年 | 52勝 | 53勝 | 3 |
| 合計 | 1174勝 | 1310勝 | 76 |
歴代の交流戦優勝球団
歴代の交流戦優勝球団を見てみましょう。
2005~2014年は「セ・パ交流戦優勝チーム」、2015~2018年は「最高勝率球団」という名称でした。
| 年度 | 交流戦優勝チーム | 勝敗 |
| 2005年 | 千葉ロッテマリーンズ | 24勝11敗1分 |
| 2006年 | 千葉ロッテマリーンズ | 23勝13敗 |
| 2007年 | 北海道日本ハムファイターズ | 18勝5敗1分 |
| 2008年 | 福岡ソフトバンクホークス | 15勝9敗 |
| 2009年 | 福岡ソフトバンクホークス | 18勝5敗1分 |
| 2010年 | オリックス・バファローズ | 16勝8敗 |
| 2011年 | 福岡ソフトバンクホークス | 18勝4敗2分 |
| 2012年 | 読売ジャイアンツ | 17勝7敗 |
| 2013年 | 福岡ソフトバンクホークス | 15勝8敗1分 |
| 2014年 | 読売ジャイアンツ | 16勝8敗 |
| 年度 | 最高勝率球団 | 勝敗(勝率) |
| 2015年 | 福岡ソフトバンクホークス | 12勝6敗(勝率.667) |
| 2016年 | 福岡ソフトバンクホークス | 13勝4敗1分(勝率.765) |
| 2017年 | 福岡ソフトバンクホークス | 12勝6敗(勝率.667) |
| 2018年 | 東京ヤクルトスワローズ | 12勝6敗(勝率.667) |
| 年度 | 交流戦優勝球団 | 勝敗 |
| 2019年 | 福岡ソフトバンクホークス | 11勝5敗2分 |
| 2020年 | 中止 | 中止 |
| 2021年 | オリックス・バファローズ | 12勝5敗1分 |
| 2022年 | 東京ヤクルトスワローズ | 14勝4敗 |
| 2023年 | 横浜DeNAベイスターズ | 11勝7敗 |
| 2024年 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 13勝5敗 |
球団別の交流戦通算成績
| 球団 | 勝敗 |
| ①福岡ソフトバンクホークス | 251勝157敗18分(勝率.615) |
| ②千葉ロッテマリーンズ | 216勝191敗19分(勝率.531) |
| ③北海道日本ハムファイターズ | 218勝196敗12分(勝率.527) |
| ④読売ジャイアンツ | 215勝198敗13分(勝率.521) |
| ⑤オリックス・バファローズ | 214勝201敗11分(勝率.516) |
| ⑥阪神タイガース | 202勝210敗14分(勝率.490) |
| ⑦埼玉西武ライオンズ | 203勝212敗11分(勝率.489) |
| ⑧中日ドラゴンズ | 201勝212敗13分(勝率.487) |
| ⑨東北楽天ゴールデンイーグルス | 204勝217敗5分(勝率.485) |
| ⑩東京ヤクルトスワローズ | 201勝215敗10分(勝率.483) |
| ⑪横浜DeNAベイスターズ | 179勝236敗11分(勝率.431) |
| ⑫広島東洋カープ | 176勝235敗15分(勝率.428) |
交流戦の魅力

- 別リーグのチームや選手を見られる
- 異なるルールでの試合
- ペナントレースへの影響
別リーグのチームや選手を見られる
別リーグのチームや選手を見られるのが、交流戦の魅力です。
ひいきチームの試合を見ていると、同リーグのチームや選手に詳しくなる一方で、別リーグを見る機会は少なくなりがち。しかし、交流戦では普段あまり見ない、別リーグのチームや選手を見られます。
- 実際に試合を見て、強いチームだと感じた
- 名前は知っていたけど、どのような選手なのか交流戦で詳しく分かった
- 初めて見た選手だけど、すごく印象に残った
交流戦をきっかけに、チームや選手への印象が大きく変わることがあります。
異なるルールでの試合
異なるルールでの試合も、交流戦の魅力。
普段、セリーグは「指名打者なし」、パリーグは「指名打者あり」で試合を行っています。しかし、交流戦では、セリーグ球団もパリーグのホーム球場で、指名打者を使用します。
また、パリーグ球団は、セリーグのホーム球場で指名打者を使用できません。投手が打席に立ちます。パリーグの投手が打席に立つのは、交流戦ならでは。
交流戦では、リーグで異なるルールにも注目しましょう。
ペナントレースへの影響
交流戦の成績が、ペナントレースに影響するのも魅力。
交流戦の成績はシーズン成績に含まれます。交流戦の成績やチームの好不調は、ペナントレースに大きな影響を与えます。
極端な話をすると、同リーグ内で1球団のみが「ひとり勝ち」「ひとり負け」する可能性もあるのが交流戦。
過去にも、交流戦をきっかけに浮上したチーム、思わぬ苦戦を強いられて低迷したチームがありました。
交流戦開始前と終了後で、両リーグの順位がどう変化しているかにも注目です。
まとめ
2005年から始まった交流戦、プロ野球ファンにすっかり定着しました。筆者も、普段あまり見ないチームとの試合が楽しみです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
→【プロ野球】パリーグとセリーグの違いは?【人気のセ・実力のパ】
→プロ野球中継を見るおすすめの方法!スカパー?DAZN(ダゾーン)?